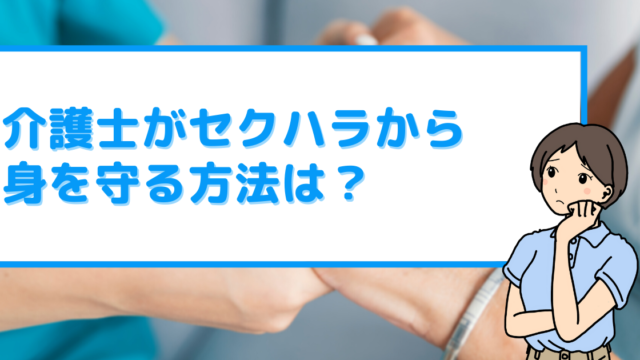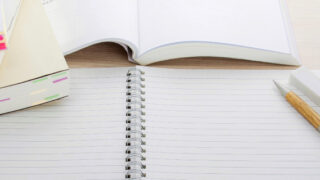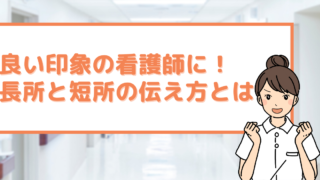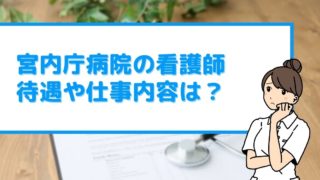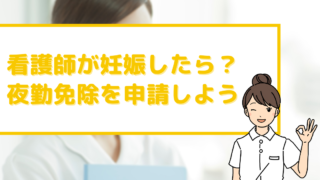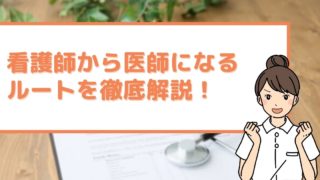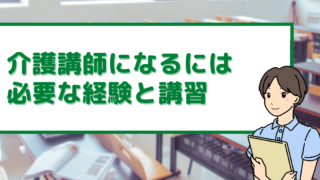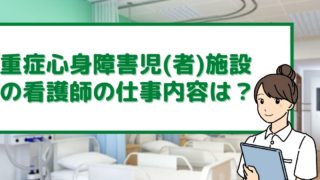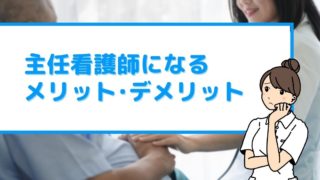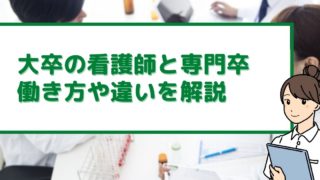介護技術に自信があって、今よりさらに収入が欲しいと考えたとき、“独立”の二文字が思い浮かぶこともあるでしょう。
しかし、「もしも失敗したら…」「収入が上がるどころか下がるかも…」と不安で動き出せずにいる人は少なくないはず。
本記事では、介護職で独立するにあたって、気になる年収事情や必要な準備について解説。
前半では『介護職で独立するのに必要な準備』について、後半では肝心の『年収事情』について触れています。
社会貢献度の高いビジネスですから、しっかり備えて成功させましょう。
また「介護職で年収1000万」を目指したい方は、こちらで解説を行っていますのでぜひ確認してみてくださいね。
目次
介護職で独立するには?

介護職での独立には、主に2つの形があります。
- 介護施設を経営する
- ケアマネージャー事務所を開く
介護職の独立というと、前者が一般的ですね。
では、介護施設を経営するためにはどのような準備が必要なのでしょうか?
1つずつ見ていきましょう。
資格を取得する

介護事業を開業するには、サービス提供責任者(通称“サ責”)の存在が必須です。
サービス提供責任者になるためには、以下の資格のうちどれか1つを取得していなければなりません。
- 介護福祉士
- 准看護師・看護師
- 介護職員実務者研修
- 保健師
上記以外では介護職員初任者研修が挙げられますが、3年以上の実務経験が必要+介護報酬が10%減算になるため、今回は除外します。
介護福祉士

介護職における唯一の国家資格です。
そのため通常の介護業務を行うだけでなく、介護職員やヘルパーへの指導およびアドバイスも行います。
資格を取得するには、以下の3つのルートがあります。
- 3年以上の実務経験を経て、実務者研修を修了して国家試験を受験
- 福祉系高校を卒業して国家試験を受験
- 指定の養成施設を卒業して国家試験を受験
どのルートもある程度の時間を要しますが、一生モノの資格なので介護業界で働き続けたい方は取得をおすすめします。
准看護師・看護師

看護師は介護福祉士と同じ国家資格ですが、准看護師は都道府県知事学校の免許となります。
- 准看護師…中学校卒業が必須条件。必要課程を修了し、准看護師試験を受験
- 看護師…中学校卒業が必須条件。大学または3年以上の必要課程を修了し、看護師国家試験を受験
主な就労先はご存知の通り医療現場で、医師の指示に従って診察や治療のアシスタントを行います。
資格取得のための期間や費用が異なるものの、どちらかの資格を取得していればサービス提供責任者になることが可能です。
介護職員実務者研修

質の高い介護サービスの提供を目標とした資格で、本的な介護提供能力の取得を目的としています。
- 450時間・6ヶ月の研修を受講し、修了判定を受ける
介護福祉士を実務経験ルートで受験するにあたって必須の資格となっていますが、450時間のカリキュラムを修了する必要があるなど簡単には取得できません。
介護職員初任者研修を修了していれば受講時間の一部が免除されるため、ステップアップとして受講する方が多いようです。
保健師

保健師助産師看護師法における「保健指導に従事することを生業とするもの」が保健師です。
- 看護師免許を取得後、保健師養成課程(1年)を修了して国家試験を受験
- 大学や4年制の専門学校等の看護師・保健師統合課程を修了し、看護師国家試験に合格してから保健師国家試験を受験
あまり聞き慣れないですが、健康診断を受けたあとに、「健康のことで心配事はないですか?」といった相談に乗ってくれる方がそうです。
このように個人の相談に乗るだけでなく、コミュニティ全体に生活改善のためのアドバイスやサポートを行い、より健康的な生活が送れるように尽力しています。
資金を貯める

介護業界に限らず、独立する上で重要になってくるのが“資金”です。
どれだけ綿密な事業計画を立てても、十分な資金がなければ成功までの道のりを走り抜けることはできません。
一概に「これだけあれば大丈夫!」と言えるものではありませんが、「おおよそこれくらいあれば大丈夫だろう」という金額をご紹介します。
運営資金として500万~1,000万円

介護事業の売上はサービスの利用者から1割、介護報酬から9割が支払われます。
しかし、後者の介護報酬はサービス提供の翌々月末(3ヶ月後)まで入金されません。
つまり、開業した月の入金はほぼゼロで、2ヶ月目であってもまだ少ない利用者からの1割程度しか入金がないということになります。
この状態で数カ月間も営業をしなければならないため、家賃や人件費を賄えるだけの資金をしっかり用意しておきましょう。
訪問介護事業なら設備資金がかからない?

介護施設を経営する場合、設備を整えるために多額の資金を投入する必要があります。
一方で、訪問介護事業は基本的に利用者宅でサービスを提供するため、他の介護事業ほど設備投資が必要ありません。
そのため新規参入しやすい介護ビジネスとして注目を集めています。
助成金について調べる

事業を展開するにあたって、「自己資金で足りない分は融資でまかなおう」と検討する方が多いはず。
でもその前に、条件さえ満たせば“返さなくていいお金”があることを知っておきましょう。
こうしたお金のことを助成金といって、国や地方公共団体が支給しています。
特定求職者雇用開発助成金

60~65際の求職者を雇うことで、“特定求職者雇用開発助成金”が受給できます。
年齢層は限られますが、介護事業に不可欠な人件費のサポートができるのは大きいですね。
主な受給要件は以下の通りです。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
次に、支給金額は以下の通りです。
| 対象労働者 | 支給額 | 対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |||
|
短時間労働者以外の者
|
高年齢者(60歳以上満65未満)、母子家庭の母等 | 60万円(50万円) | 1年 | 30万円×2期 (25万円×2期) |
||
| 重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円×4期 (25万円×2期) |
|||
| 重度障害者 | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6ヶ月) |
40万円×6期 33万円×3期 |
|||
|
短時間労働者
|
高年齢者60歳以上満65未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 | 20万円×2期 (15万円×2期) |
||
| 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円×4期 (15万円×2期) |
|||
生涯現役起業支援助成金

40歳以上の起業家を対象とした助成金制度で、従業員の雇用に関する費用を最大200万円まで支給してくれます。
雇用創出措置助成分と生産性向上助成分の2つがあり、支給額はそれぞれ以下の通りです。
- 雇用創出措置助成分
| 起業時の年齢区分 | 助成率 | 助成学の上限 | ||||
| 起業者が高年齢者(60歳以上)の場合 | 3分の2 | 200万円 | ||||
| 起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合 | 2分の1 | 100万円 | ||||
- 生産性向上助成分
「雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給
参照元:厚生労働省ー生涯現役起業支援助成金
法人形態の種類を把握する

介護事業所は営利法人の参入が認められており、近年では株式会社が主流になりつつあります。
有限会社は2006年の会社法施行で廃止されたので新たな設立はできませんが、全ての出資者が有限責任を確保されている合同会社であれば設立可能です。
営利法人以外では社会福祉法人や医療法人など、社団法人に分類される非営利法人が認められており、いずれも経営者自身は無資格でも問題ありません。
失敗例を調べる
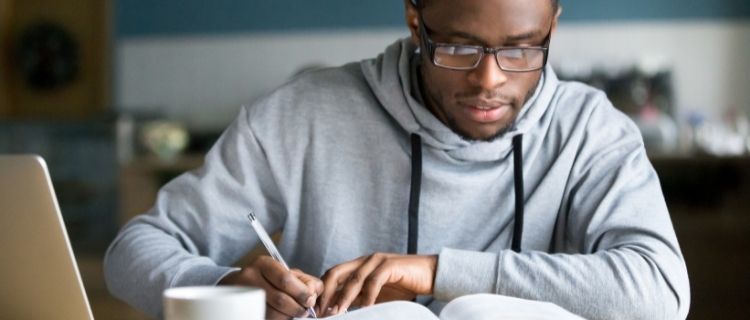
介護業界に新規参入する場合、過去の失敗例を調べておくことで成功確率を大幅に上げることができます。
では、どんな理由で失敗しているのかというと、
- 開業資金を調達できなかった
- 十分な人材を確保できなかった
上記2つが多くの割合を占めているようです。
融資が受けられない、想定よりも応募がないなんてことはよくあるので、十分な自己資金を用意したり、人脈を駆使するなどしてリスクに備えましょう。
介護事業オーナーの年収事情

介護事業所をどうにか開業できたとして、経営者になると同時に年収は上がるものなのでしょうか?
調べてみると「社員として働いているときの方がよかった」「開業当初は生活できるギリギリの収入しかなかった」という方もいるようです。
本項では介護事業オーナーの収入はどのように決定して、どれくらいの金額になるのかを、介護事業の利益率から考えてみましょう。
介護事業の利益率は3%前後

厚生労働省による令和元年度の「介護事業経営概況調査」によると、利益率は平均すると3%ほどのようです。
利益率が高いところだと認知症対応型通所介護7.4%、夜間対応型訪問介護5.4%が挙げられます。
新規参入しやすい訪問介護も4.5%と高めですが、介護老人福祉施設は1.8%、小規模多機能型居宅介護は2.8%と3%を下回る結果となりました。
利益率を高めるには⇒回転率を上げる

少子化にともなって人材不足はますます深刻化することが予想されるので、スタッフ一人あたりの利用者の数を増やすことが売上げアップにつながります。
しかし、それによって提供する介護サービスの質が低下するようなことがあってはいけません。
徹底的な業務効率化でできる限り負担を抑えつつ、回転率を上げるようにしましょう。
利益率を高めるには⇒規模を大きくする

さらなる利益を求めるためには、施設を大きくする、複数の事業所を営業するなど規模を大きくする必要があります。
違う角度から見るなら“経営の多角化”と言ってもいいでしょう。
利用者のあらゆるニーズを分析し、実現可能なものからはとり入れて他の介護事業者との差別化を図ります。
年収は450万~1,000万円

今後ますますの需要増が見込まれる介護業界ですが、参入しやすいからといって成功しやすいというわけではありません。
上手く利益を出すことができれば年収1,000万円も可能ですが、事業継続=成功とするなら平均年収は700万円ほどとなります。
ただし、「どうにか継続できている」という状況では年収は450万円ほどにまで下がります。
正社員よりは多いものの、仕事量を考えたときに「つらい」という気持ちが先行するかもしれません。
小さな介護施設運営が成功のカギ?

前項で利益率を高めるためには規模を大きくすると記載しましたが、小さな介護施設運営が成功のカギを握ると注目を集めています。
介護事業は数あれど、いずれにしても介護施設との連携が重要で、この連携ができなればわずかな利益を追いかけることになるでしょう。
つまり、介護施設を経営すれば介護サービスの連携がスムーズになり、利益をきっちり残せるようになるのです。
小さな介護施設は収益性が高い?

介護報酬だけでなく医療報酬を受け取れるサービス(訪問看護)を自社で運営し、1部屋あたりの賃料(原価)を5万円以下に抑えましょう。
コストをコントロールできれば20床程度の小さな介護施設でも、売上を十分に確保できる計算になります。
さらに、介護度3以上の方向けの施設にすることで、高い収益確保がより現実的なものとなります。
収益性が高い=高待遇を用意できる

収益を確保できれば、近隣相場よりも良い条件の待遇が用意できるようになります。
介護スタッフといえども人間ですから、少しでも良い条件で働きたいのが本音ではないでしょうか。
モチベーションの高いスタッフが集まれば、会社の利益は自然と増えていきます。
そして利益が増えれば再びスタッフに還元すると言った具合に、良いサイクルが小規模だと作り出しやすいのです。
介護事業は将来性有望で新規参入しやすい!

介護ビジネスのマーケットは、2025年には現在の約2倍となる20兆円まで膨れ上がると言われています。
ここだけ見ると成功する予感しかしないと思いますが、ビジネスである以上は綿密な事業計画と準備がなければ成功はおろか継続すらできません。
とはいえ、今後の急成長が確実視されている業界ですので、収益を上げられる仕組みと働きやすい環境を作り出すことができれば成功は目前です。
介護する人とされる人、双方のクオリティ・オブ・ライフを尊重しながら、年収1,000万円の経営者を目指しましょう。