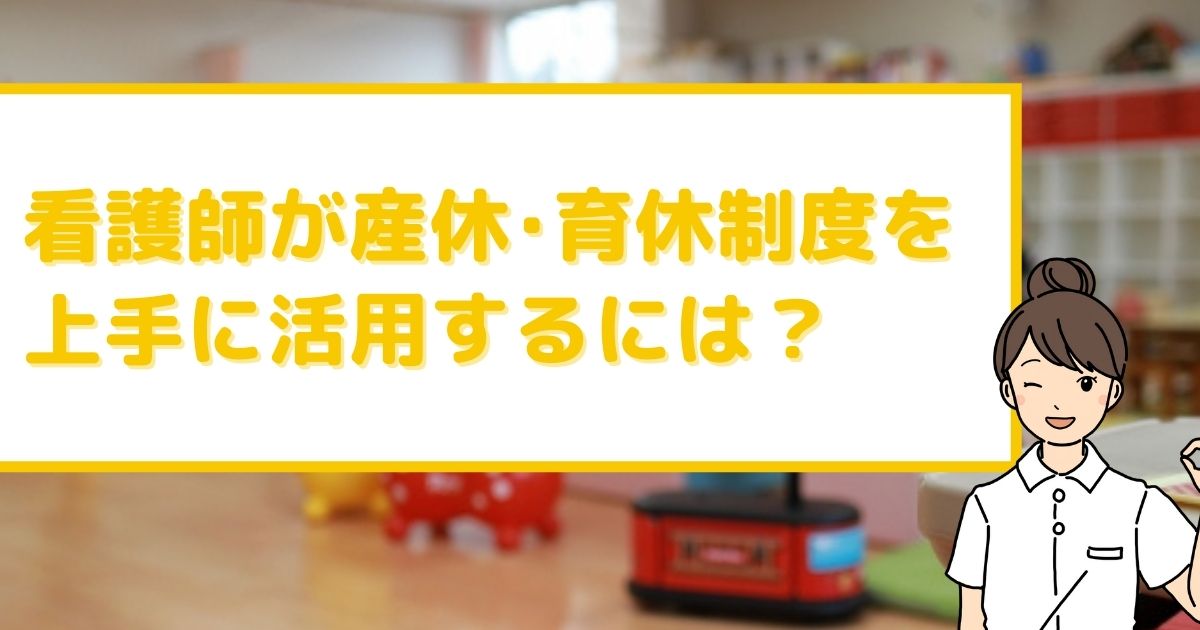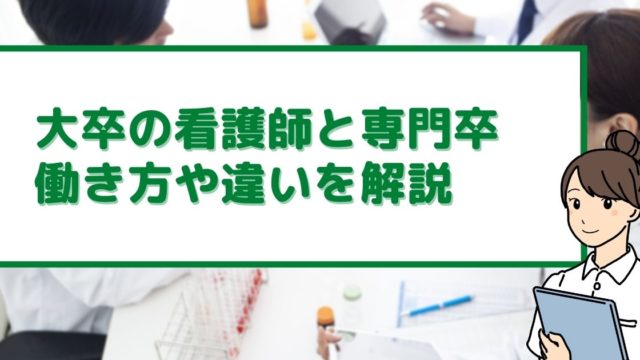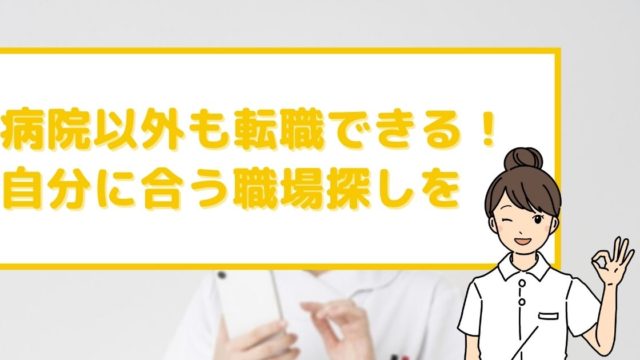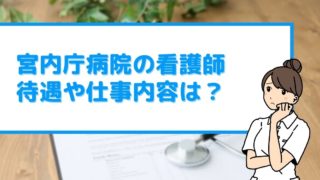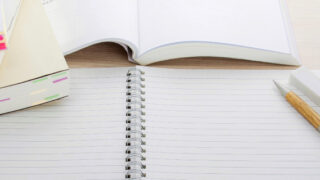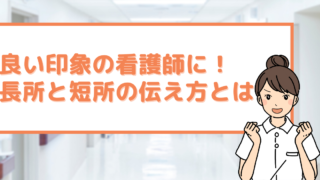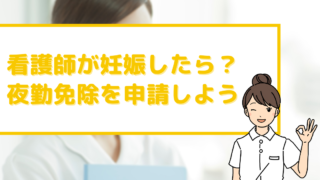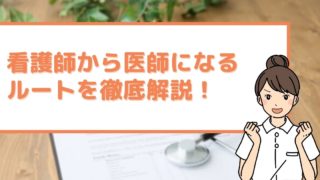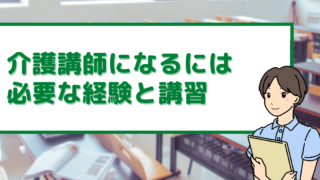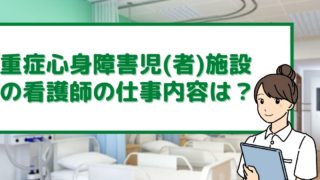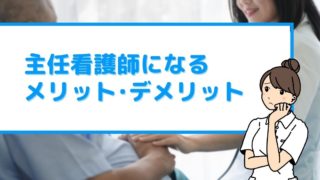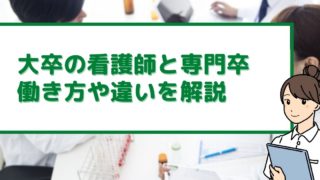妊娠が分かったとき、喜びと同時にこんなことを考えませんでしたか?
「仕事は続けられる?」
「辞めなければいけない?」
「もし産休を取れても、給料はどうなる?」
特に看護師としてバリバリ働いているなら、不安はより大きなものになるでしょう。
この記事でお伝えするのは、産休や育休の制度を上手に利用するための方法です。
休業中の手当や妊娠報告のタイミングについても解説しているので、ぜひご覧ください。
目次
1.看護師でも産休は取れる!
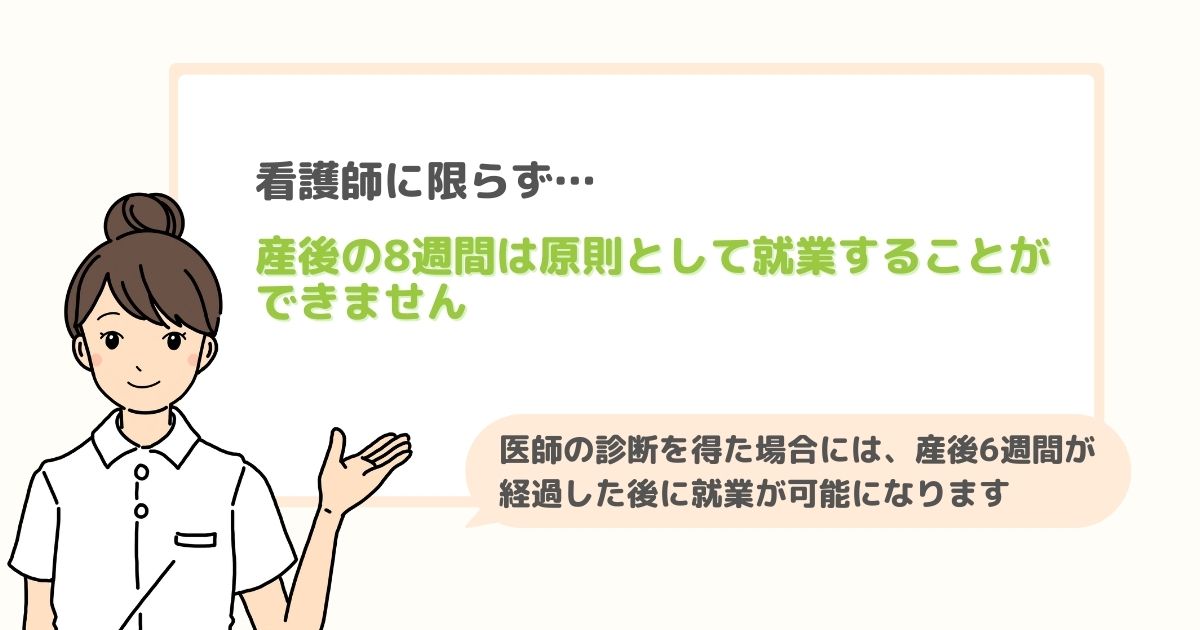
産休は、職業や雇用形態も関係なく取得することが可能です。
看護師も例外ではありません。
さらに産休について詳しく知るために、以下の2点に情報をまとめました。
- 産休とは
- 産休の期間
それぞれ見ていきましょう。
(1)産休とは
産休とは、労働基準法で定められている、産前産後休業のことです。
自身の職場に請求することで必ず取得可能で、会社側はそれを拒否することはできません。
基本的には、妊娠を伝えた時点で取得する流れになるでしょう。
産前休業の取得を望まない場合は、その旨を職場に伝えることで休まず働き続けることも可能です。
しかし、産後の8週間は原則として就業することができません。
これは、母体保護が目的のためです。
詳しくは、次の項目で説明します。
(2)産休の期間
産休の期間は、労働基準法における母性保護規定で以下のように定められています。
- 産前6週間以内
- 産後8週間以内
- 双子以上の場合は、産前14週間以内
つまり、通常の妊娠では、産前と産後を合わせて14週間の取得が可能ということです。
前述の通り、産後は必ず休まなければいけません。
しかし、医師の診断を得た場合には、産後6週間が経過した後に就業が可能になります。
どうしても早く職場復帰したいという場合には、頭に入れておきましょう。
2.看護師でも育休は取れる?
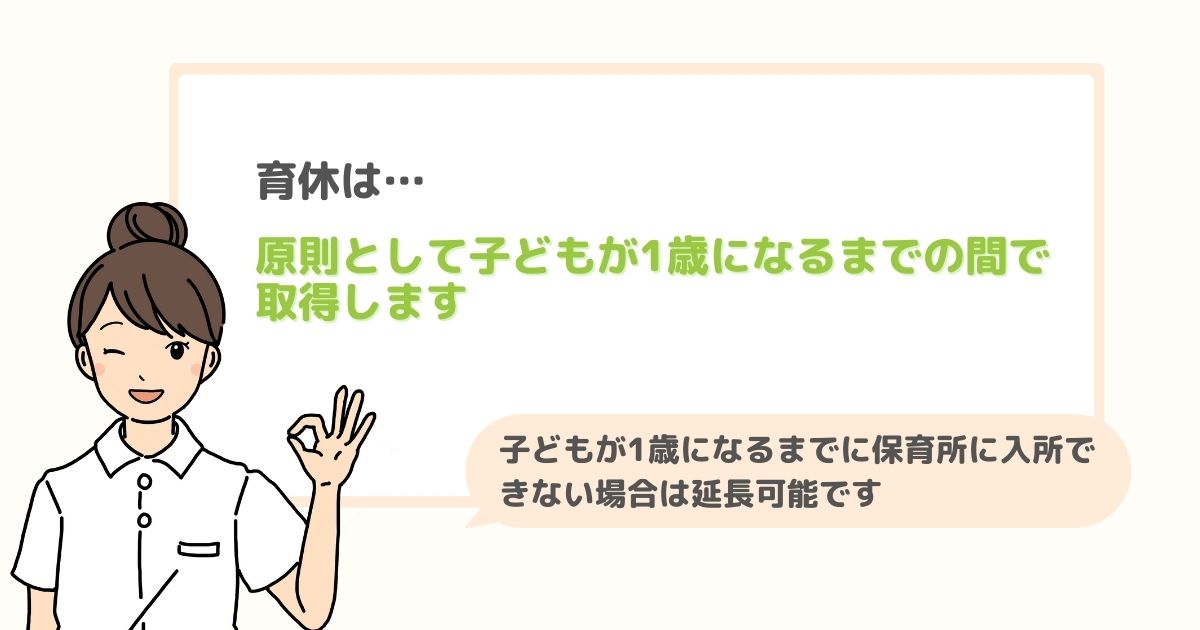
こどもが生まれたら、少しでも長く一緒に過ごしたいと考えるのではないでしょうか。
そんなとき、産休と合わせて知る必要があるのが、育休についてです。
ここでは、2点に分けて解説していきます。
- 育休とは
- 育休の期間
それでは、見ていきましょう。
(1)育休とは
育休とは、育児・介護休業法で定められた、子を育てるための休業を指します。
厚生労働省の定義での正式名称は、育児休業。
産休と育休は、同じタイミングで取得することも多いです。
しばしば混同して認識される産休と育休ですが、様々な違いがあります。
ここでは、特に重要な違いである取得条件を見てみましょう。
育休取得の条件
産休では、出産していること以外に取得条件がありませんでした。
育休では、どのように定められているのでしょうか?
条件は以下の3点です。
- 子どもが1歳に満たない
- 1年以上継続して雇用されている
- 休業終了後も引き続き雇用される見込みがある
育休は、原則として子どもが1歳になるまでの間で取得します。
条件として、1年以上の雇用期間が無い場合の休業は、法律には定められていません。
法的な強制力がないため、休業の判断は会社に委ねられます。
また、育休は復帰を前提とした休業です。
休業後に退職することが分かっている場合は、利用できません。
次は、育休の期間について見ていきましょう。
(2)育休の期間
前述のように、育休の期間は、原則として子どもが1歳になるまでの間です。
しかし、例外として、最長2年の取得が認められています。
例外となるのは、子どもが1歳になるまでに保育所に入所できない場合です。
その場合は、6か月の期間延長が認められます。
さらに、その期間中に入所できない場合、加えて6か月の育休取得が可能です。
全てを合計すると、子どもの誕生から最長で2年になります。
待機児童の問題もあるため、覚えておいて損はない情報ではないでしょうか。
3.看護師が産休・育休で受けられる経済支援
産休・育休について、知識を深めてきました。
次に心配になるのは、休業中の金銭面ではないでしょうか。
休業中は働いていないため、基本的に会社から給料をもらうことはありません。
そんなときに知っておきたいのは、経済支援・手当についてです。
ここでは、産休・育休中に受けられる経済支援について、以下の4点で解説します。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 社会保険料の免除
それでは、見ていきましょう。
(1)出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険法によって定められた、出産の際の分娩費用を軽減する手当です。
子どもを1人出産すると、42万円が支給されます。
子どもの人数分支給されるため、双子の場合84万円、3つ子の場合は126万円です。
支給方法は、出産の費用として医療機関に対して支払われる直接支払制度が一般的。
分娩費用が42万円以下で済んだ場合には、差額が手元に戻ってくることもあります。
不安な場合には、分娩の際に利用する医療機関に質問してみましょう。
直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度をしないことに特にメリットはありません。
しかし、利用する医療機関によっては、直接支払制度に対応していないこともあるでしょう。
その場合、書類で申請をする必要があります。
基本的には、会社の総務が申請方法や必要書類を把握しているはずです。
そのため、本人記入欄を埋めて総務に提出する流れになるでしょう。
(2)出産手当金
出産手当金は、健康保険加入者の産休中に支給されます。
申請方法は、勤務先で貰う出産手当支給申請書を記入、提出するだけです。
支給される金額は、給料の約2/3になります。
以下の表に、おおよその支給額を記載しました。
|
過去12か月の平均額面給与額 |
一日当たりの出産手当金 |
出産手当金の総支給額 |
|
20万の場合 |
4,444円 |
435,512円 |
|
25万の場合 |
5,555円 |
544,390円 |
|
30万の場合 |
6,666円 |
653,268円 |
これは、あくまでも簡易的に理解するために作成したものです。
詳しい支給額の計算方法は、記事の最後にまとめてご紹介しています。
(3)育児休業給付金
育児休業給付金では、育休中の収入を確保することができます。
取得条件は2つです。
- 子どもが1歳未満であること
- 過去2年間の中で、12か月雇用保険に加入していること
基本的に、勤続1年以上であれば問題ありません。
申請先はハローワークですが、手続きは会社の総務が行うことがほとんどです。
不安な場合は、総務に確認しましょう。
育児休業給付金の支給額は、実際の給料の約67%で、1か月単位で支給されます。
おおよその支給額をまとめた表はこちらです。
|
過去12か月の平均額面給与額 |
1か月あたりの給付額 |
6か月の総支給額 |
|
20万の場合 |
133,987円 |
803,922円 |
|
25万の場合 |
167,493円 |
1,004,958円 |
|
30万の場合 |
201,000円 |
1,206,000円 |
育児休業給付金の詳しい計算方法も、記事の最後に記載しました。
気になる場合は、ぜひご覧ください。
(4)社会保険料の免除
産休・育休中には、社会保険料の免除も受けられます。
免除期間中は、厚生年金や健康保険の支払いが無くなり、年金の受取額の減額もありません。
本人記入の書類などはあるものの、申請を行うのは、勤務先の会社です。
もし免除されない等のトラブルがあった場合には、会社の総務に問い合わせましょう。
産休と育休の両方を取得した場合、約13か月の免除期間が生まれます。
お金を受け取ることはないため、あまり実感が湧かないかもしれません。
しかし、月々の収入が下がっている休業中には、欠かすことのできない支援といえるでしょう。
4.看護師が妊娠報告をするタイミング
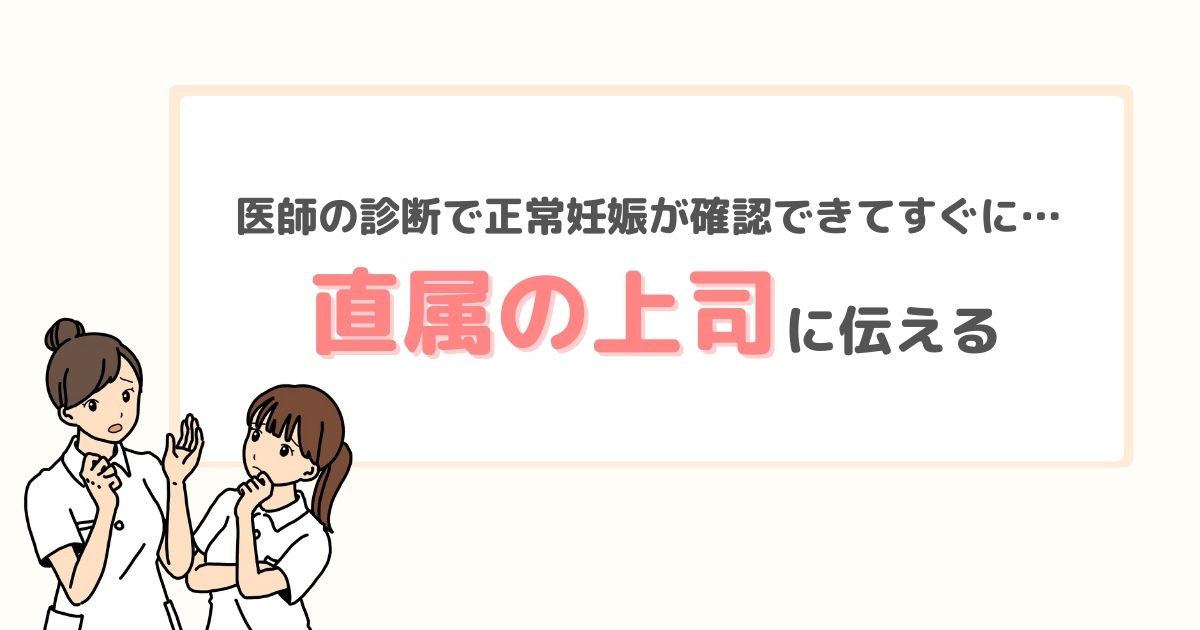
産休を取るためには、会社に妊娠報告をしなければいけません。
妊娠発覚から、どれくらいのタイミングで報告するべきでしょうか。
おすすめは、医師の診断で正常妊娠が確認できてすぐです。
看護師のあなたなら、妊娠初期がとても大事な時期であることは分かりますね。
職場の周りの人は、妊娠を知らなければ配慮することもできません。
体調を気遣いながら仕事をするためにも、早めの妊娠報告を心掛けましょう。
妊娠報告は誰に伝える?
初めての妊娠では、報告を誰に伝えればいいか分からないですよね。
一番最初に報告する相手は、直属の上司に伝えましょう。
上司に一番に伝える理由は、職場の人間関係を壊さないためです。
仲のいい同僚に伝えたくなる気持ちも分かります。
しかし、もし噂が広まってしまった場合には、同僚を疑わなければいけません。
また、噂として広まってしまうと、聞きつけた上司も良い印象を抱かないでしょう。
そのため、妊娠は上司を通じて職場に通知することが安全といえます。
5.看護師が産休・育休の申し出で知っておきたいこと
上司に妊娠を報告した際、産休・育休の取得希望についても聞かれるでしょう。
申し出のときまでに、考えをまとめておくことでスムーズな調整が可能です。
事前に知っておきたいことを、以下の2点にまとめました。
- 上司から確認されること
- 用意・記入の必要があるもの
それぞれ確認していきます。
(1)上司から確認されること
妊娠を報告したとき、上司から確認されるであろうことを簡単に見てみましょう。
- 出産予定日
- 最終出社予定日
- 復帰の希望
- 育児休業の取得の有無
復帰の希望や育休は、今後の生活にも関わる重要な選択ともいえます。
家族との話し合いが必要になるかもしれません。
その場の考えで簡単に決めてしまうのではなく、後悔のないように事前に決めておきましょう。
(2)用意・記入の必要があるもの
総務部がある会社では、基本的に必要な手続きや申請は行ってくれるでしょう。
必要になる書類には、自分で記入しなければいけないものも含まれています。
難しいことは一切ありませんが、どのようなものがあるか簡単に把握しておきましょう。
- 産前産後休業届
- 保険出産手当金申請書
- 母子健康手帳
特に、母子健康手帳は様々な手続きに必要になります。
使う機会も多いため、取り出しやすい所に大事に保管しておくと良いかもしれません。
5.看護師は産休と退職のどっちを選ぶべき?
ここまで看護師が産休・育休を取って職場復帰する場合について見てきました。
産後も働くと決めている場合、産休を取得しないという選択肢もあります。
特に、産休が取りづらいと感じている場合には、退職して転職することも考えるかもしれません。
ここでは、退職・転職した場合のメリットとデメリットについて考えてみましょう。
- 産休を取らずに転職するメリット
- 産休を取らずに転職するデメリット
それぞれ解説します。
(1)産休を取らずに転職するメリット
産休を取らずに転職するメリットは、転職の機会になるということです。
働いている職場がどうしても嫌で辞めたい場合には、良い口実になります。
転職する際は、育児支援を行っている職場を選ぶことも可能です。
病院に転職するのであれば、メジャーな育児支援として院内保育が挙げられます。
出産を機に、ワークライフバランスを見直すことも良いかもしれませんね。
(2)産休を取らずに転職するデメリット
産休を取らないデメリットは、金銭面です。
退職すると産休や育休の経済支援は、ほとんど受けられなくなります。
退職しても受けられる経済支援は、出産育児一時金だけです。
つまり、100万円以上の損をしているといっても過言ではありません。
また、退職ではキャリアが途切れてしまうことも、後の給料に響いてきます。
退職を考える際には、このようなデメリットがあることも忘れないようにしましょう。
6.看護師の産休・育休から職場復帰する時に知っておきたいこと
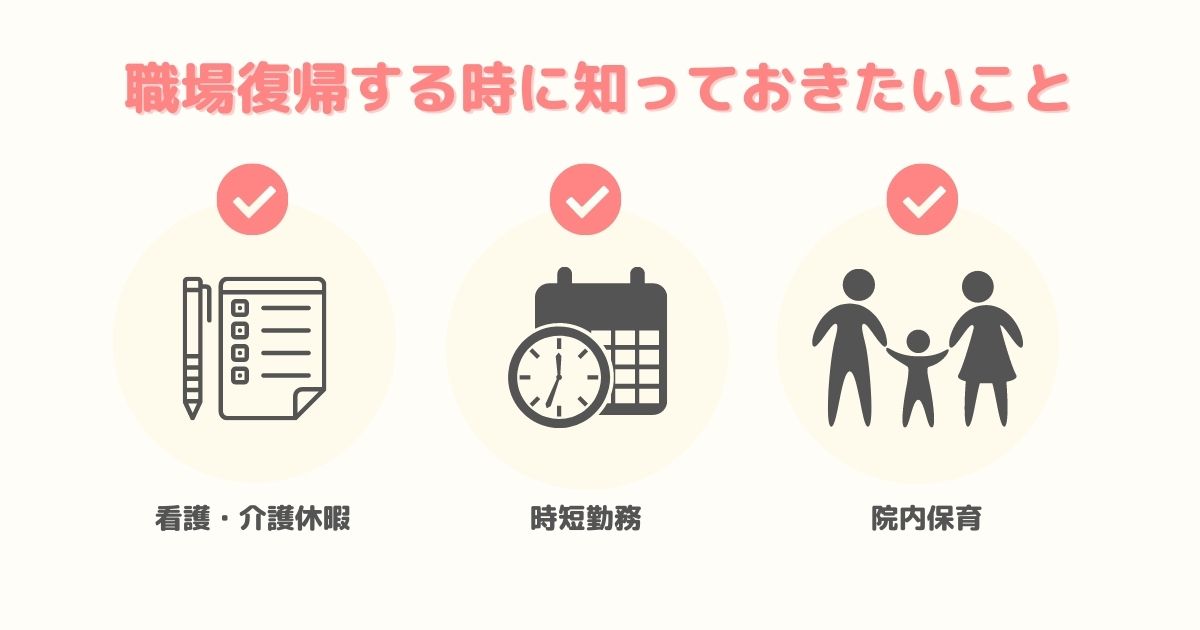
産休・育休を無事に取った後、職場復帰する際は悩むことが増えるはずです。
なぜなら、子育てと仕事で板挟み状態になってしまうから。
ここでは、そんなワーキングマザーが知っておくと便利なことを紹介します。
- 看護・介護休暇
- 時短勤務
- 院内保育
それぞれ解説していきます。
(1)看護・介護休暇
子どもの体調不良時には、急な休みを取らなければいけないことも出てきます。
そんなときに役立つのが、看護・介護休暇です。
厚生労働省が公表している、看護・介護休暇の取得要項を見てみましょう。
- 未就学の子ども1人につき年間5日まで
- 子ども2人以上で年間10日
また、法改正により令和3年の1月1日から、時間単位での取得が可能になります。
より使い勝手が良い休暇制度になるため、覚えておいて損はありません。
(2)時短勤務
フルタイムで働きながら、育児も行うとなると難しさがあるかもしれません。
その場合には、時短勤務の申請ができます。
時短勤務は、育児・看護休業法で認められている働き方です。
この制度を利用することで、雇用形態は正社員のまま、所定労働時間を6時間にして働くことができます。
期間は、子どもが3歳になるまで利用可能です。
注意点として、給料は時短分だけ減ってしまうことを覚えておきましょう。
(3)院内保育
病院によっては、院内保育を行っている場合があります。
職場で子どもを預かってもらうことで、安心感もあるのではないでしょうか。
料金面でもメリットがあり、通常の保育園よりもお得になることがあるようです。
病院では、病児保育も行っている場合もあります。
院内保育を利用できれば、仕事と育児の両立にとても役立つでしょう。
【解説】産休・育休中の経済支援の具体的な計算方法
記事中で紹介することができなかった、2つの手当の具体的な計算方法について説明します。
- 出産手当金
- 育児休業給付金
順を追って説明しているので、きっとご理解いただけるはずです。
それでは見てみましょう。
(1)出産手当金の具体的な計算方法
出産手当金の具体的な計算は、全国健康保険協会が公表しています。
ここでは簡単に理解するために、2つの値に分けました。
- 1日当たりの出産手当金
- 出産手当金の総支給額
それぞれ見ていきましょう。
計算1.1日あたりの出産手当金
1日あたりの出産手当金の計算は、このような式で表すことができます。
| 1日あたりの出産手当金支給額の計算式 |
| 標準報酬月額÷30×2/3 |
標準報酬月額は、過去12か月の額面給料を平均したものです。
手取り額ではなく、額面で計算を行います。
例として、標準報酬月額が25万円の場合を見てみましょう。
| 例)標準報酬月額が25万円の場合 |
| 250,000÷30×2/3=5,555 |
標準報酬月額が25万円の場合、1日あたりの出産手当金支給額は5,555円であることが分かります。
次に、総支給額の計算を見てみましょう。
計算2.出産手当金の総支給額
出産手当金の総支給額を求める式は、以下のようになります。
| 出産手当金の総支給額の計算式 |
| 1日あたりの出産手当金×98 |
産休では、産前と産後を合わせて、98日の休みを取得できます。
そのため、1日当たりの出産手当金に休んでいる日数である、98を掛けた値が総支給額となるわけです。
先ほどと同じように、標準報酬月額が25万円の場合の例を見てみましょう。
| 例)標準報酬月額が25万の場合 |
| 5,555×98=544,390 |
標準報酬月額が25万円の総支給額は、約54万円と分かりました。
このように式に数字をあてはめるだけで、簡単に計算できます。
難しく感じた場合は、1つずつ順番に計算しましょう。
(2)育児休業給付金の具体的な計算方法
厚生労働省の情報を元に、育児休業給付金の計算方法をまとめました。
ここでは、3つに分けて解説していきます。
- 休業開始時賃金日額の計算
- 育児休業給付金
- 育休を6か月を超えて取得した場合
それぞれ見ていきましょう。
計算1.休業開始時賃金日額
育児休業給付金の金額を求めるためには、休業開始時賃金日額という値が必要です。
休業開始時賃金日額は、以下の式で求めることができます。
| 休業開始時賃金日額の計算式 |
| 育児休業開始前6か月の総支給額÷180 |
例として、6か月の平均額面給与が25万円の場合の式を見てみましょう。
| 例)平均額面給与が25万の場合 |
| 250,000×6÷180=8,333 |
平均額面給与が25万円の場合はの休業開始時賃金日額は、8,333円であると分かりました。
次に、本題の育児休業給付金の求め方を見ていきます。
計算2.育児休業給付金
育児休業給付金の支給は1か月単位です。
先ずは、1か月の育児休業給付金を求める式から見てみましょう。
| 育児休業給付金の1か月の給付額 |
| 休業開始時賃金日額×30×67% |
例として、平均の額面給与が25万円の場合の式を見てみます。
| 例)平均額面給与が25万の場合 |
| 8,333×30×67%=167,493 |
平均の額面給与が25万円の場合の1か月分の給付額は、約17万円となりました。
次は、育休6か月以降の計算方法です。
計算3.育休を6か月を超えて取得した場合
次に、育休が6か月を超えた場合の計算方法を見ていきます。
育休は、最大で2年間の取得が可能です。
その間も給付金は支給されますが、ひと月の割合は50%に減額します。
こちらが、育休6か月以降の給付額の計算式です。
| 育休6か月以降の1か月の給付額 |
| 休業開始時賃金日額×30×50% |
平均の額面給与が25万円の場合の例を見ます。
| 例)平均の額面給与が25万円の場合 |
| 8,333×30×50%=124,995 |
平均額面給与が25万円のとき、6か月までとそれ以降では、ひと月の給付額に約4万円の差が生まることが分かります。
| 育児休業給付金の1か月の給付額 | 167,493 |
| 育休6か月以降の1か月の給付額 | 124,995 |
保育施設が見つからない場合には、減額を踏まえた家計のやり繰りを考えましょう。
まとめ
看護師が産休・育休を上手に取得する方法について解説してきました。
産休は、どんな職業でも取れます。
それは看護師でも同じです。
看護師のように忙しい仕事では、休むことに多少の申し訳なさを感じるかもしれません。
しかし、出産を控えた妊婦が体を大事にするのは当たり前のことです。
生まれてくる子どものためにも、重要ですよね?
申し訳なく思う気持ちは、仕事に復帰したときに挽回すればいいです!
子育ての第一歩の役目を果たし、万全の状態で仕事復帰できるようにしましょう!