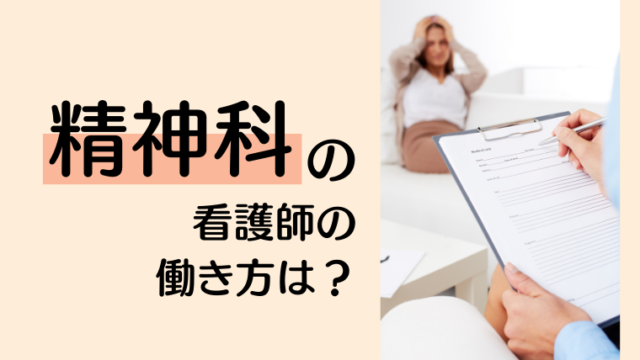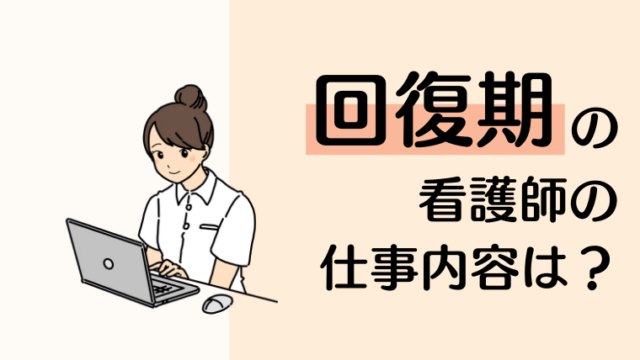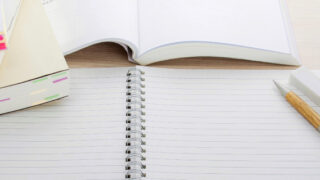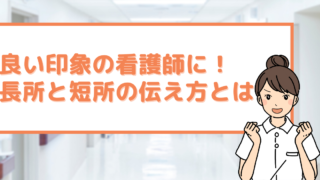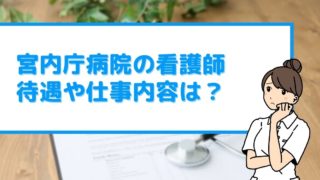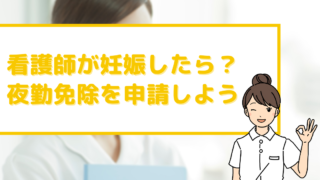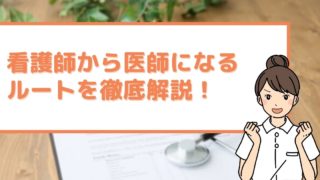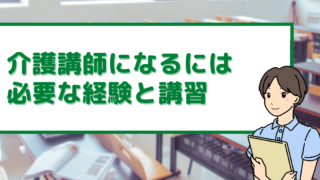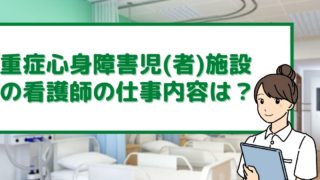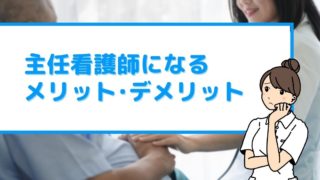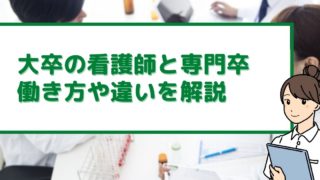「今の職場が激務のわりに給料が安い…」
「公務員看護師は給料が良いってきいたけど、どうやったらなれるの?」
そんな悩みを抱えていませんか?
もしあなたがそんな風に悩んでいるなら、ぜひこの記事を最後まで読んでみてください。
今回は公務員看護師についてメリット・デメリット、求人の探し方まで詳しく解説しています。
調べてみて改めて、公務員は待遇面でメリットが多いことがわかりました。
給料や手当、ボーナス等収入面の充実のほか、プライベートを犠牲にしない働き方も導入されています。
現在の職場の待遇に不満がある人には、転職に向けての1つのヒントになるかもしれません。
ぜひ最後までお読みくださいね。
目次
1.公務員として働く看護師とは?
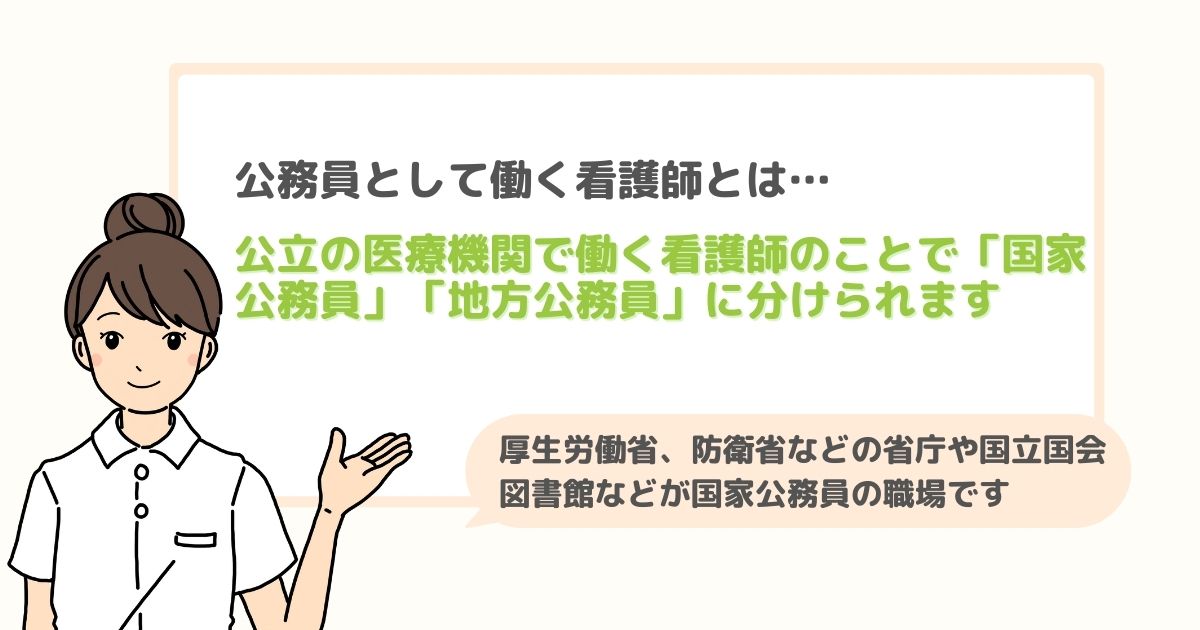
公務員看護師とは公務員として公立の医療機関で働く看護師のことです。
公務員は大きく分けて2つに分類することができます。
1つは「国家公務員」、もう一つは「地方公務員」です。
国家公務員は国が運営する機関に勤める公務員、地方公務員は都道府県や市町村など自治体に勤める公務員のことを言います。
厚生労働省、防衛省などの省庁や国立国会図書館などが国家公務員の職場です。
自衛隊員も防衛省に属する特別職国家公務員ということになります。
一方で地方公務員は県庁、市役所に勤める職員、また公立の小学校に努める教員も地方公務員です。
さて、国家機関や地方自治体にも看護師を必要とする機関が存在します。
例えば国立ハンセン病療養所や県立病院、市立病院などです。
国立ハンセン病療養所は国(厚生労働省)の運営する医療機関ですし、県立病院は県が、市立病院は市が運営する病院ですね。
こういった国や自治体の運営する医療機関で働く看護師は、看護師であり公務員という立場です。
仕事内容は民間の看護師と同じですが、「全体の奉仕者」という公務員の立場で看護の仕事を行うことになります。
では次の章からはさらに具体的に公務員看護師の職場を解説していきいますね。
一緒にみていきましょう!
2.公務員看護師の種類は?
それではこの章で公務員看護師が働く職場を具体的にみていきましょう。
公務員看護師の職場は大きく分けて2つに分類できます。
前章で書いた通り「国家公務員」と「地方公務員」によって職場の性質が少しことなるからです。
この章でも国家公務員看護師の職場と、地方公務員の職場にわけてみていきますね。
- 国家公務員としての看護師
- 地方公務員としての看護師
1つずつみていきましょう。
(1)国家公務員としての看護師
まずは国家公務員看護師が働く職場からみていきます。
看護師が国家公務員として働く職場はそれほど多くありません。
国家公務員自体が全体の2割しかおらず、さらにその中でも看護師という専門職はさらに数が限られるからです。
そんな希少な国家公務員看護師はどんな所で働いているかというと、以下のような施設で働いています。
以下の表は国家公務員看護師が働く機関・役職名、管轄省庁とその機関・役職の説明をまとめた表です。
| 機関名・役職名 | 管轄省庁 | 説明 |
|---|---|---|
| 国立ハンセン病療養所看護師 | 厚生労働省 | ハンセン病後遺症の対応と、高齢化からくる疾患の予防・対処に当たっている医療施設 |
| 宮内庁病院看護師 | 宮内庁 | 皇室の方々や宮内庁職員が受診する病院 |
| 自衛隊看護師 | 防衛省 | 自衛隊病院や自衛隊衛生科で働く看護師 看護師であり自衛隊隊員、特別職国家公務員 |
| 看護技官 | 厚生労働省 | 看護の専門性を活かして厚生労働省の行政を行う国家公務員、看護師資格の他に助産師、もしくは保健師の資格が必要 |
| 検疫官 | 厚生労働省 | 港湾や空港の検疫所で感染症などの検疫衛生業務にあたる国家公務員 応募資格に「看護師免許取得」がある |
| 刑務所看護師/法務技官看護師 | 法務省 | 医療刑務所で働く看護師 / 収容者の看護業務に当たる看護師 |
ご覧いただくとわかる通り、どの機関も特殊な環境であったり看護師にプラスしてさらに資格が求めらる職場がほとんどです。
募集数も少なく応募資格条件も厳しいのでなかなかの狭き門と言えるでしょう。
(2)地方公務員としての看護師
次に地方公務員看護師の職場をみていきましょう。
地方公務員看護師の主な職場になるのは、都道府県立病院や市町村立病院です。
こちらは国家公務員看護師に比べると看護師の数も多くなります。
都道府県立と市町村立の病院を合わせると全国で約850あり、国の運営する医療機関に比べればかなり数が多いからです。
このように都道府県立病院、市立病院などが地方公務員看護師の主な職場になります。
国立大学病院勤務は「準公務員」
「国立大学病院で働く看護師は国家公務員ではないの?」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
実は国立大学病院で働く看護師は国家公務員ではありません。
なぜなら 国立大学病院は「国立病院機構」という独立行政法人によって運営されているからです。
全国154カ所の国立病院・国立療養所は平成16年に独立行政法人に移行しました。
そのため、厳密に言うと国家公務員ではありませんが国家公務員に準ずる立場の機関ということになります。
以上が公務員看護師の種類と職場でした。
どんなところで働くかイメージできたのではないでしょうか?
では次の章で公務員看護師になるメリットについてみていきたいと思います。
公務員ならではの安定した待遇はやはりメリットになりそうです。
次の章で詳しくみていきましょう。
3.公務員看護師のメリットは?
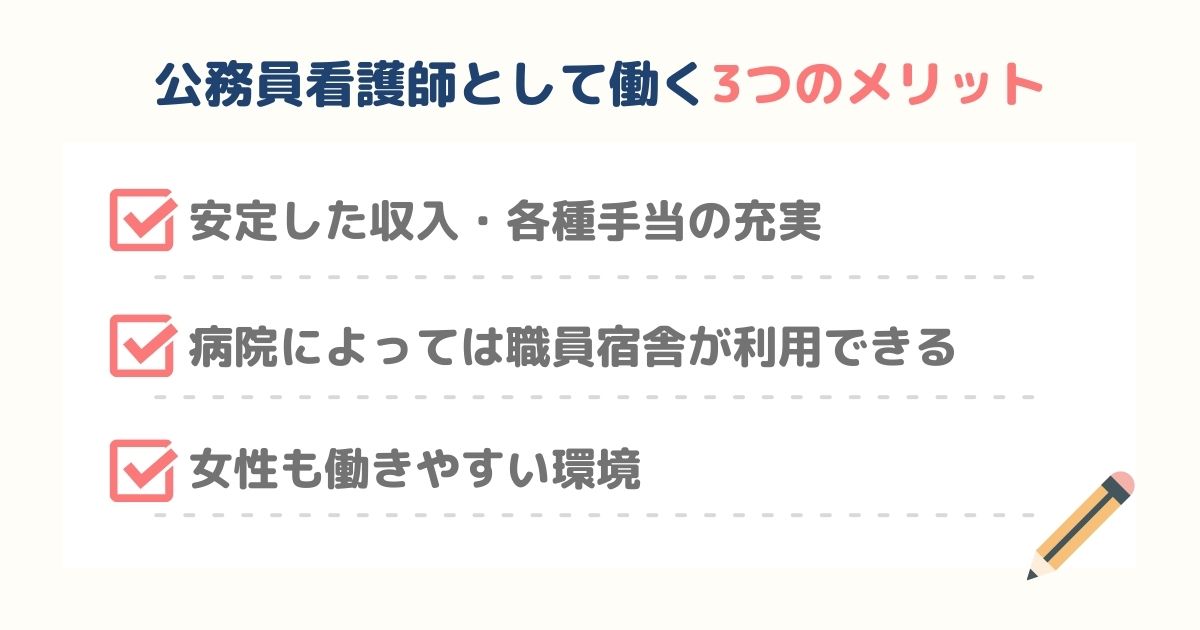
それではこの章で公務員看護師になるメリットについて深くみていきましょう。
メリットは全部で3つです。
- 安定した収入・各種手当の充実
- 病院によっては職員宿舎が利用できる
- 女性も働きやすい環境
1つずつみていきましょう。
(1)安定した収入・各種手当の充実
公務員看護師のメリットの1つ目は、何といっても安定した収入と言えるでしょう。
なぜなら公務員は営利目的の団体ではないので、業績によって左右されないからです。
民間企業の場合近年は能力給を導入しているところも多いため、年齢が上がるからといって必ずしも給料が上がるとは限りません。
一方公務員は無断欠勤など問題行動なく普通に勤務していれば年を追うごとに給料は上がっていきます。
次の表は総務省が発表している「平成30年地方公務員給与の実態」という資料の抜粋です。
平成30年の大卒の都道府県一般行政職員の勤続年数と給料の変化を表しているのでみてみましょう。
| 勤続年数 | 平均給与月額 |
|---|---|
| 1年未満 | 185,039円 |
| 1年以上2年未満 | 191,656円 |
| 2~3 | 198,860円 |
| 3~5 | 210,822円 |
| 5~7 | 227,341円 |
| ~中略~ | ~中略~ |
| 20~25 | 370,943円 |
| 25~30 | 391,680円 |
| 30~35 | 411,339円 |
| 35年以上 | 424,165円 |
見ていただくとわかる通り勤続年数が上がるにつれて毎月の給料もあがっていますよね。
公務員は各種手当が充実していることもメリットです。
国家公務員がもらえる手当の一部を書き出してみました。
(※参考:人事院「国家公務員の給与」 P10)
生活補助的手当:
- 扶養手当
- 住居手当
- 通勤手当
- 単身赴任手当
地域給的手当:
- 地域手当(民間の賃金水準が高い地域に在勤する職員に最大20%支給)
- 広域異動手当
- 特地勤務手当
- 寒冷地手当
時間外手当:
- 超過勤務手当
- 宿日直手当
その他:
- 俸給の特別調整(民間でいうところの管理者手当)
- 専門スタッフ職調整手当(重要度・困難度の高い業務に従事するスタッフに支給)
ここでは一部だけ挙げましたが、全部で20個近くの手当が設定されています。
月の給料に対して手当がどのくらいの割合を占めるか、人事院の発表している資料があるのでみてみましょう。
以下の表は人事院の発表している平均年齢43.4歳の国家公務員の給与の構成例です。(P11)
| 俸給(基本給にあたる部分) | 329,433円 |
| 地域手当・広域異動手当 | 43,540円 |
| 俸給の特別調整額(管理職手当) | 12,659円 |
| 扶養手当 | 10,059円 |
| 住居手当 | 6,121円 |
| 単身赴任手当 | 9,311円 |
| 合計: | 411,123円 |
「通勤手当」と「超過勤務手当」は実費で支払われるのでこの表には記載がありません。
実費手当を除いた手当の合計ですでに80,000円を超えることからも、公務員の手当が充実していることがわかりますね。
最後にボーナスですが、これに関しても公務員と民間企業で大きく差が出るところです。
民間企業は業績によってはボーナスが出ない年もありますが、公務員はよほどのことがない限りボーナスは毎年支給されます。
なぜなら公務員のボーナスは「期末手当」・「勤勉手当」という手当の一部にあたり、手当の支給は法律でも謳われていることだからです。
このように公務員の給料に関しては法律で定められているためよほどのことがない限り支給されるのです。
令和2年10月初旬に、その年の公務員ボーナスが10年ぶりに引き下げられたことがニュースになっていました。
公務員のボーナスは民間と足並みをそろえる仕組みになっているため、新型コロナの影響による民間の業績悪化を反映したからです。
「民間と足並みをそろえる」といっても、民間企業との差は大きいと感じます。
今年はボーナスを何割か減らす、もしくは支給しないと発表している企業もある中公務員は4.45ヶ月分は支給されるからです。
やはり民間と比べて安定性があると言えますよね。
国や国民への奉仕者という立場の公務員なので、その立場はきっちりと守られているということが垣間見れる例だと思います。
看護師も公務員であれば例外ではありませんから、このような安定した収入は大きなメリットと言えるでしよう。
(2)病院によっては職員宿舎が利用できる
公務員看護師になると家賃が節約できるかもしれません。
なぜなら職員宿舎を用意している病院もあり、職員は格安で利用できるからです。
賃貸アパートやマンションの家賃は毎月の大きな支出ですよね。
かといって、持ち家でない限り毎月家賃を払っても住まいは確保しなければなりません。
都道府県立の病院の中には職員宿舎を用意しているところがあります。
例えば埼玉県立病院の例をみてみましょう。
こちらの病院では病院から徒歩5~15分圏内に看護師公社を用意していて、毎年ほぼ希望者全員が入居できているそうです。
驚くべきはその家賃の安さで、管理費別で月2,900円~16,600円と記載されています。
埼玉県立病院の所在地であるさいたま新都心駅周辺のワンルームの家賃相場が57,400円なので、格安であることがわかりますね。
埼玉県立病院に限らず、公立病院が用意する看護師宿舎は家賃や相場に比べてかなり格安に抑えられています。
しかも病院への通勤が楽な場所に建てられる傾向にあるので通勤で満員電車に揺られる負担もありません。
家賃も抑えられ通勤時間も減るので、懐にも体にも優しく大きなメリットと言えるでしょう。
(3)女性も働きやすい環境
女性が働きやすい環境が手に入るもの公務員看護師のメリットと言えるでしょう。
なぜなら政府が力を入れている「女性活躍推進」や「働き方改革」は民間の中小企業よりも公務員に早く反映されるからです。
「働き方改革」や「女性活躍推進」に関しては国や地方自治体、社員数301人以上の大企業にはすでに具体的な動きが求められています。
例えば行動計画の作成と届け出、実施状況の報告、公表などです。
ですが中小企業に対してはいまだ「努力義務」でとめられており強制力はありません。
今後は中小企業にも普及してくるでしょうが現状はまだまだ行きわたっていないのが実情です。
公務員が先をいっているかと言えば必ずしもそうではありませんが、国からの縦割りの指示が届きやすいので改善も早いと言えます。
また働き方改革や女性活躍推進が取りざたされる前から公務員の方が女性に優しい側面もありました。
例えば出産後の育児休暇は公務員の場合生後3年まで取得可能です。
民間では出産後3年休ませてくれる会社はそうそうありませんから、公務員の条件がいいのがわかりますよね。
公務員看護師に限っていうと女性の働きやすさはどうなのでしょうか。
例として静岡県立病院看護部の福利厚生をみてみると、家庭と仕事の両立がしやすくなる制度がたくさん盛り込まれています。
お子さんの学校行事への参加などの場合に使える「家族休暇」の取得や、小学校就学前のお子さんのいる職員は時短勤務も可能です。
さらに、生後間もないお子さんのいる職員は午前中と午後に1回ずつ60分の休憩をとれる「生児保育」という制度もあります。
仕事で家族を犠牲にしないような配慮がなされているのが女性にとってはありがたく働きやすい職場といえるでしょう。
こうやってみてみると、公務員看護師のメリットはたくさんありますよね。
では公務員看護師になることのデメリットはあるのでしょうか?
それを次の章でみていきましょう。
4.公務員看護師のデメリットは?
先ほどの章では公務員看護師のメリットについて詳しくみてきました。
この章では公務員看護師のデメリットについて解説していきますね。
公務員看護師のデメリットですが、まず就職が簡単ではないことでしょう。
なぜなら採用人数が限られていて小論文や面接の試験を突破しなければならないからです。
例えばこちらの千葉県立病院の例をみてみましょう。
令和2年9月に千葉県職員(看護師)の選考試験が行われていますが、募集は県全体で20名だけです。
千葉県には県立病院が6つあるので、単純計算で1つの病院に3名しか採用枠がないことになります。
作文試験と面接があるとのことなので対策が必要ですが、試験の過去問は公表していないらしいので試験対策がむずかしいですね。
新潟県の募集もみてみましょう。
新潟県では令和3年4月1日から勤務の県職員看護師を令和2年8月31日から10月2日の間で募集していました。
採用は34名と千葉県より多いですが、新潟県立病院は全部で13でこちらも単純計算で1病院あたり3名弱の枠となります。
どちらの県についても県全体で数十名の採用枠しかないので、合格を勝ち取るのは決して簡単ではないはずです。
この「狭き門を突破しないとなれない」というのが公務員看護師のデメリットでもあります。
また能力給の要素が薄く、勤続年数が上がるごとに給料も増える給与体系に不満を覚える人もいるかもしれません。
向上心が高く仕事熱心な人にとってはモチベーションが下がる状況かもしれませんね。
安定しているがゆえに離職率も低く、人間関係の風通しが悪くなるのもデメリットの1つと言われています。
以上が公務員看護師のデメリットでした。
では最後に公務員看護師になるにはどうしたらいいかを次の章で解説していこうと思います。
次の章で最後なので、あと少しついてきてくださいね!
5.公務員看護師になるには?
それでは公務員看護師になるためにどのような手順を踏んだらいいか、また求人の探し方などをみていきましょう。
- 求人の探し方は?
- 地方公務員看護師の試験内容は?
- 地方公務員看護師の年齢制限は?
上記3つの観点から説明しています。
1つずつみていきましょう。
(1)求人の探し方は?
国家公務員看護師を目指す場合、その医療機関を管轄する省庁のホームページをこまめにチェックするようにしましょう。
なぜなら国立の医療機関はそれぞれ管轄する省庁がちがい、それぞれの省庁ごとに募集をかけるからです。
国立ハンセン病療養所なら管轄は厚生労働省、宮内庁病院は宮内庁、自衛隊病院なら防衛省、というように管轄がわかれます。
看護師の募集に関してもそれぞれの省庁が行っているため、管轄省庁の発表する募集情報を逐一チェックするしかありません。
随時募集をしているところもあれば不足が出た場合のみ募集をかける所もあります。
目指す役職がある場合は募集情報を逃さないようにしましょう。
次に地方公務員看護師の求人の探し方についてです。
都道府県立病院の看護師を目指す場合、まずはその自治体のホームページを確認しましょう。
新潟県は県のホームページで県立病院の看護師の募集要項が掲載されていました。
もう1つの方法は先に県立病院個別のホームページに入り、その病院の「採用情報」を確認することです。
例えば「新潟県立病院」と検索するといくつか県立病院の名前が検索に上がってきます。
その中から1つどこでもいいので病院のホームページに入ってみましょう。
今回は例として「新潟県立がんセンター」を選んでホームページを見てみます。
新潟県立がんセンターのホームページ上の「看護師募集」のバナーををクリックすると県職看護師の募集要項にとぶことができました。
このように地方公務員看護師の募集情報は、自治体のホームページから探すか個別の病院のホームページから探すのがいいでしょう。
なお、募集日程や回数、募集人数は各自治体によって様々で一律のきまりは無いようです。
新潟県は年1回の募集ですが静岡県は年に4回、1期~4期にわけて試験を実施しています。
参考までに北海道・東北、関東甲信越、関西、九州・沖縄から例を1つずつとって募集時期と回数を表にまとめてみました。
| 地域 | 代表自治体 | 募集時期・回数など |
|---|---|---|
| 北海道・東北地区 | 北海道 | 令和2年度は6,8,10,12,1月の計5回募集 |
| 関東甲信越 | 東京都 | 令和3年4月1日からの新卒採用を1回、令和2年度の経験者採用は5,7,8,10月に4回実施 |
| 関西地区 | 大阪府 | 令和3年4月1日からの採用を3回、中途採用は8,9,10,11月の4回実施 |
| 九州・沖縄地区 | 福岡市 | 令和3年4月1日から採用分の採用試験を6月に1回のみ |
人口の多い自治体は年に数回募集をかけていますし、地方では年1回のみの募集になるところもあるようです。
自分が応募したい自治体の募集スケジュールを把握してチャンスを逃さないようにしましょう。
また地域にこだわらない場合は、採用人数が多く募集を年に数回やっているような自治体を受けてみるのも1つの手かもしれません。
(2)地方公務員看護師の試験内容は?
地方公務員看護師の採用試験の内容に関しては自治体毎にそれほど違いはありません。
なぜならほとんどの自治体で「小論文」と「面接(口頭試験)」の2項目の試験を実施しているからです。
新潟県のように小論文と面接にプラスして「適性検査」という項目を設けている自治体もあります。
また小論文の過去問については公表していない自治体もあれば、青森県のように過去問例を公表しているところもありました。
詳しくは、各自治体の募集要項を参考にしましょう。
(3)地方公務員看護師の年齢制限は?
地方公務員看護募集の年齢制限ですがこれも自治体によって違います。
いくつか例を挙げてみたのでご覧ください。
- 新潟県 昭和51年4月2日以降に生まれた人(現44歳)
- 北海道 採用予定日現在で59歳未満
- 川崎市 令和3年3月31日時点で60歳未満の人
- 静岡県 昭和36年4月2日以降に生まれた人(現59歳)
多くの自治体は採用日の時点で60歳未満であることを条件にしていますが、新潟県のように低めの年齢制限を設けているところもあります。
こちらも各自治体の募集要項をよく確認するようにしましょう。
まとめ
以上が公務員という立場で働く看護師についての調査でした。
希望すれば誰でもなれるものではなくハードルは低くありませんが、公務員ならではの待遇の良さは大きな魅力があります。
「働き方改革」や「女性活躍」などの政策もすでに反映されているため、女性にとっては
働きやすい環境が望めるでしょう。
現在の職場での激務や待遇に悩んでいる人がいるなら、公務員という働き方も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
あなたの看護師としてのキャリアがより良いものになるよう応援しています!